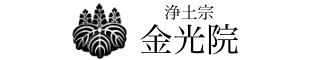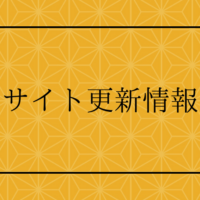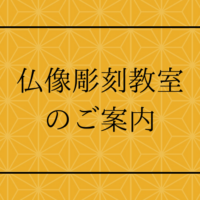

住職挨拶 ~「開かれたお寺」を目指す金光院~

金光院のホームページにご訪問いただき、誠に有難うございます。
住職の戸川克彦(とがわ こくげん)と申します。
先代から住職を引き継いで、令和5年現在で早13年になりました。この13年という月日は短いようで長いもので、元号は平成から令和に変わりましたし、世界中が未曾有のパンデミックと長く険しい戦いを経験することにもなりました。価値観や生活様式が目まぐるしく変化するこの時代に、私たち「お寺」はどうあるべきなのか。どんな役割が求められているのか。お寺を取り巻く環境も変わりつつあるように感じます。
浄土宗の宗祖・法然上人は、平安末期から鎌倉初期にかけての激動の時代の中、繰り返される内乱や災害、疫病によって疲弊する人々を見て、誰もが救われる世を目指して浄土宗を開き、世に広めました。
そんな法然上人の想いを現代へと受け継ぐ浄土宗派の一寺院として、私たち金光院は、檀家信徒さまだけでなく地域にお住まいの方や京都に観光しに来てくださった方々まで、より多くの人たちとの交流を深め、人々に「笑顔」や「安らぎ」を届けられる場所でありたいと願っております。
お寺という空間をうまく活用し、ひとつひとつのご縁を大切にしていくことで、「お寺をもっと開かれた場所へ。地域や社会に貢献できる場所へ。そして、もっともっとHappyな場所へ」を目指し、日々精進を重ねていきたい所存です。

お寺をもっと開かれた場所へ、もっとHappyな場所へ
このような考えに至るきっかけとなったのは、誰しもが外出することさえ憚られ、人と人との繋がりが希薄になってしまったコロナ禍での経験でした。
京都には観光客で賑わう寺院がたくさんありますが、すべてのお寺がその限りではありません。歴史的な建造物や由緒ある宝物、偉人にまつわるエピソードなどを持たない当院のような小さな寺院の場合、訪れてくださるのは檀信徒さまくらいのものです。そんな檀信徒さまたちとの交流の機会も、葬儀や法事のご依頼さえも、コロナ禍には激減してしまいました。
「このままでは寺院の運営すらままならないかも知れない。460年続く金光院の歴史が、私の代で途絶えてしまうかも……?」
そんな危機感すら覚えるようになりました。幸いにもコロナ禍の混乱は収束に向かい、世間も次第に平常を取り戻していきましたが、激動する時代の中で、寺院運営の在り方も見つめ直していかなければならないと感じ始めたのです。

そんな焦りも抱えながら過ごしていた令和4年5月のある夜、寺庭にふと目を向けると、小川の周りを数匹のホタルが飛び回っている姿が目に写りました。青紅葉や紫陽花の間を飛び交うホタルたちが織りなす、儚くも美しい自然の神秘に、思わず目が奪われます。
「この景色を、ぜひもっとたくさんの人たちにも見てもらいたい……!!」
そう思い立ち、急遽「ホタルの鑑賞拝観」を実施したのです。Instagramでの呼びかけも功を奏し、遠方からもたくさんの方が当院を訪れてくださいました。ピーク時には20匹以上のホタルが池の周りを乱舞し、ホタルたちが織りなす幻想的な光景に、たくさんの方からのご好評をいただくことができました。
「こんなに近くでホタルを見たのは初めてです!」
「うちの子はホタルを見るのは初めてで、もう大はしゃぎです」
「綺麗ですねぇ…… 最近はホタルを見られる場所も少なくなりましたし、素敵な景色を見れてよかったです」
ホタル拝観を通してたくさんの人たちと会話を重ね、多くのご縁を結ぶことができました。そして、皆さまから寄せられた「静かでいい場所ですね」「美しいお庭ですね」という声に、このお寺が持つ価値にも気付かされました。特別な宝物や建造物がなくても、お寺という空間には人々に安らぎや喜びを与えるだけの魅力が十分に備わっている。今の時代だからこそ「お寺」にできること、求められているものがきっとある。そんな思いが膨らみました。

そんな思いから始めたのが、「お寺で気まぐれカフェ くろ谷 金光院」です。お寺の境内で静かなときを過ごしながら、食事やお飲み物、かき氷などを楽しんでいただこうという試みです。
たくさんの方が食べに来てくださり、ご家族で「美味しい!」と賑わう姿を見て、嬉しくなりました。初めはひと夏限定のつもりで始めたカフェでしたが、常設することを決め、たくさんの交流が生まれました。
そうしていく中で、お寺という場所(空間)を利用して「開かれたお寺、そして社会貢献、地域貢献できるお寺にしたい、さらにはお寺をhappyな場所にしたい」という将来像がはっきり見えてきたのです。

時代の流れの中で、お寺の価値を再度考える
昨今の時代、お寺といえばお墓参りなどの法事の際に訪れる場所、あるいは、清水寺や銀閣寺などの「特別な観光名所」としてイメージされることが多いかと思います。しかし時代を遡ってみれば、お寺とは学業や文化、社会福祉、地域交流の中心を担う場所だったはずです。孤児やご老人、身体に障害を抱えた方や病人などに医療を提供したり、子供たちに読み書きそろばんを教えたり、何かあった際の「駆け込み寺」になったり。お寺とはもともと、人の生活と密接に結びつき、人と社会を繋ぐ地域コミュニティの中心だったのです。
時代は流れ、現代ではお寺と地域や人々との結び付きはだいぶ希薄になってしまいました。それ以前に、現代では「地域や社会と共に生きている」という感覚自体が人々の意識の中で薄れてしまっているのかも知れません。マンションの隣の部屋に住む住民の名前さえ知らないというケースも普通になりました。
でも、そんな時代だからこそ、お寺は本来の役割を取り戻す必要があるのではないでしょうか。気軽に遊びに来れる交流の場、人との繋がりを感じられるコミュニティ、困ったときにいつでも気軽に相談できる場所、そんな「みんなのお寺」を金光院は目指しています。
法然上人が浄土宗を開き、お念仏の教えを世に広めてから850年。今こそ原点に回帰し、たくさんの方々に笑顔や喜び、安らぎを届けらるようなお寺になっていけたらと思います。多くの方が気軽に金光院を訪れ、カフェやワークショップ、ほたる鑑賞、宿坊などを通して五感いっぱいにお寺を楽しんでいただけたら嬉しい限りです。お気軽に遊びに来てください。
令和5年11月10日
戸川克彦